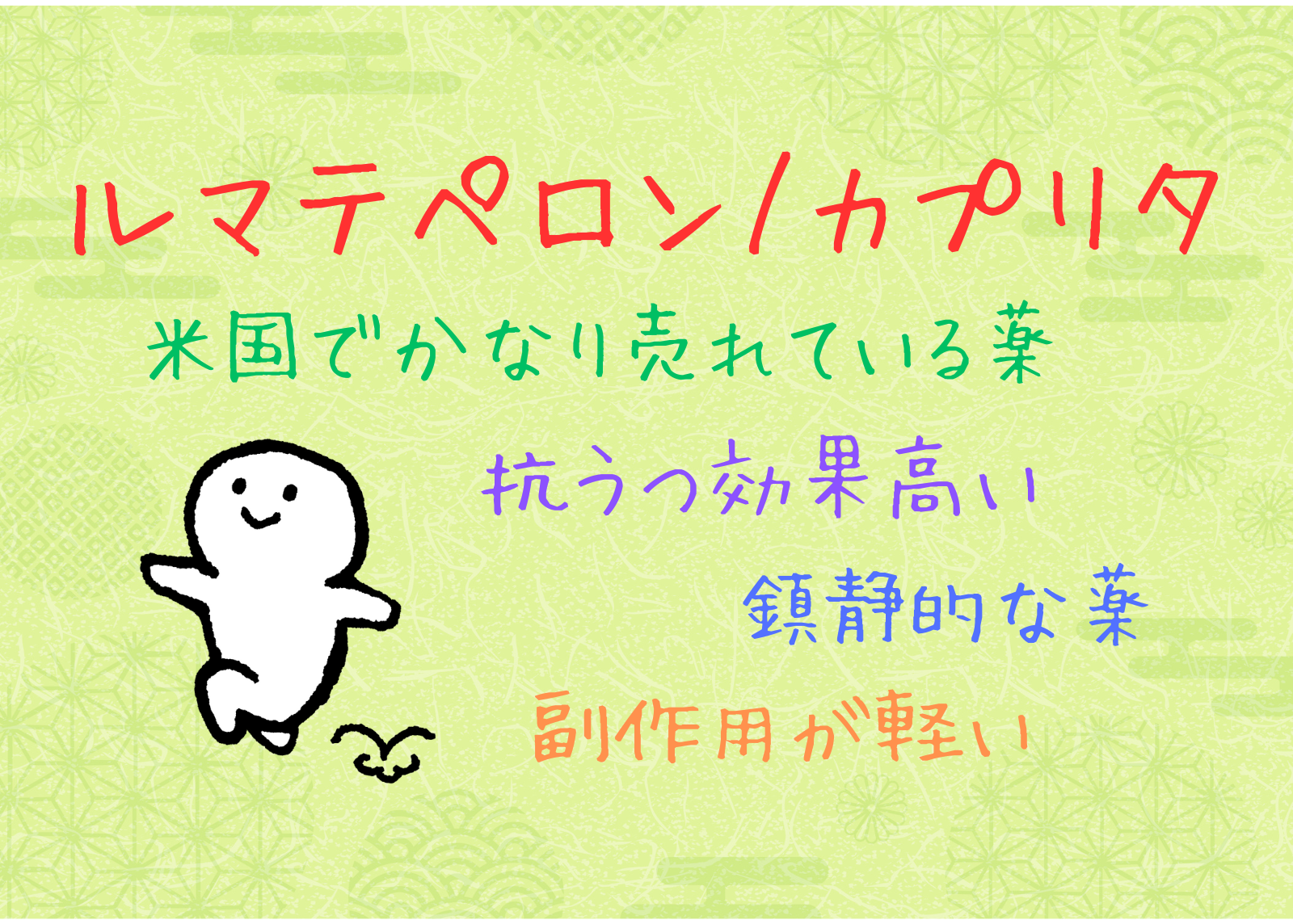はじめに
この記事では、ルマテペロンの躁うつ病のうつ状態への適応について書く。
ルマテペロンについて書いた元の記事はこちら。
ルマテペロン(カプリタ) /独特な非定型抗精神病薬/合う人には合うかも
双極うつへの有効性
ルマテペロンは、日本ではまだ開発が始まっていない。けれども、米国では既に統合失調症薬として発売されている。
さらに米国では、躁うつ病患者のうつ状態に対するフェーズ3臨床試験(治験)も行われた。
主にMADRS(Montgomery Asberg Depression Rating Scale|モンゴメリー・アスベルグうつ病評価尺度)という尺度を使って有効性が測られた。
ルマテペロン42mgが、188人の躁うつ病患者に、6週間に渡って投与された。プラセボを投与された患者は189人だった。
ルマテペロンのMADRSスコアの平均減少幅と、プラセボのMADRSスコアの平均減少幅との差は、-4.6だった。効果量は-0.56だった。
MADRSで測られた他の向精神薬が見つからなかったので、このプラセボとの差と、効果量が、大きいのか小さいのか分からない。
でも一般的に、効果量-0.56は、やや大きいように思われる。ルマテペロンは、抗うつ効果がまあまああるかもしれない。
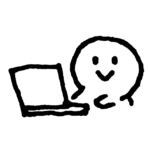
ルマテペロンの抗うつ効果は、まあまああるという結果になった。
また、統合失調症へのフェーズ3臨床試験の時と同じく、錐体外路症状や体重増加などの副作用もほとんどなかったようだ。
双極うつへの適応へ
ルマテペロンは、他にも2つ、躁うつ病患者のうつ状態に対する臨床試験が行われている。
一方の臨床試験では、再びルマテペロン単剤で、うつ状態に対する効果が調べられた。しかし、この試験では、有効性を示せなかった。
もう一つの臨床試験では、ルマテペロンが、リチウムやデパケンの補助薬として使われて、うつ状態への効果が調べられた。そして、その有効性が示された。
これらの臨床試験(治験)結果から、FDAは2021年12月に、双極性障害1型及び2型のうつ状態に対する、単剤と補助療法での販売を承認した。
今回、ルマテペロンの副作用で多かったのが眠気や鎮静で、13%に見られた。次に、めまいで、8%、吐き気も8%の患者に見られた。
日本で、ルマテペロンの治験が行われるという情報はなかった。今後、その辺りの情報も見ていきたい。
副作用が軽い
ルマテペロンの副作用については、別々の3つの臨床試験の結果を統合して、副作用や忍容性がどの程度か調査されている。その結果が最近、ある雑誌で報告された。
1073人もの患者の副作用データが統合され、解析された。内訳は、プラセボ412人、ルマテペロン406人、リスパダール255人、となっている。
その結果、治療中断率は、リスパダール4.7%、ルマテペロン0.5%、プラセボ0.5%だった。
錐体外路症状(EPS)の出現は、リスパダール6.3%、ルマテペロン3.0%、プラセボ3.2%だった。
体重増加についても、ルマテペロンとプラセボで同程度だった。
ルマテペロンにやや多かった副作用は、眠気、鎮静、口渇ぐらいだった。だいたいは穏やかな程度だった。
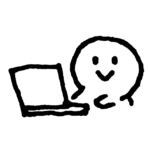
このように見てみると、確かに副作用の面では、リスパダールよりかはだいぶ良さそうだ。
ルマテペロンは、ある程度の有効性を維持しながら、良好な安全性と忍容性を持っている。
躁うつ病患者や統合失調症患者にとって、重要な薬の選択肢の1つになるだろうと言われている。
まとめ
ルマテペロンの抗うつ効果は、まあまああるという結果が出た。
日本ではまだ治験が始まっていないが、米国では、双極性障害1型及び2型のうつ状態について、販売承認が下りている。
ルマテペロンは副作用が軽い。患者にとって重要な選択肢の1つになるだろうと言われている。
コメント
ルマテペロンは、この記事で紹介した治験とは別に行われた、統合失調症に対するフェーズ3試験で、抗うつ効果や陰性症状への効果は、あまり見られなかった。
けれど、その後の躁うつ病への臨床試験などでは、まあまあの有効性を示したので、抗うつ効果や陰性症状への効果は、結構あるのかもしれない。
統合失調症のフェーズ3試験では、「急性期」の患者に対して投与されている。その時は、あまり効かなかったが、「安定期」や「維持期」の患者には、有効性を示す事もあるかもしれない。大うつ病への適応も目指されているらしい。
ルマテペロンは、脳の炎症を抑制する効果があると言っている文献もある。
Lumateperone normalizes pathological levels of acute inflammation through important pathways known to be involved in mood regulation
また、ドーパミンD1受容体依存的に、NMDA受容体やAMPA受容体を刺激する。その事によって、前頭前皮質で、ドーパミンやグルタミン酸の放出を増加させるらしい。
Lumateperone-mediated effects on prefrontal glutamatergic receptor-mediated neurotransmission: A dopamine D1 receptor dependent mechanism
これらの事によって、認知機能障害、陰性症状、うつ症状、を改善する効果があるらしい。
他の抗精神病薬にはない独特な作用を持っている。日本で発売されたら、一部の人たちには良い薬になるという事もあるかもしれない。元気が出たりする人もいるかもしれない。
関連記事はこちらです。
ルマテペロン(カプリタ) /独特な非定型抗精神病薬/合う人には合うかも
参考文献
- https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/CP02103044.PDF
- https://ir.intracellulartherapies.com/news-releases/news-release-details/intra-cellular-therapies-announces-us-fda-approval-caplytar
- https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/mood-disorders/lumateperone-safe-and-effective-for-patients-with-bp-experiencing-depressive-episodes/
- https://www.jneurosci.org/content/early/2022/12/22/JNEUROSCI.0984-22.2022
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X22002346